林 一彦 院長の独自取材記事

動物歯科クリニック 花小金井動物病院
(小平市/花小金井駅)
最終更新日: 2025/04/10
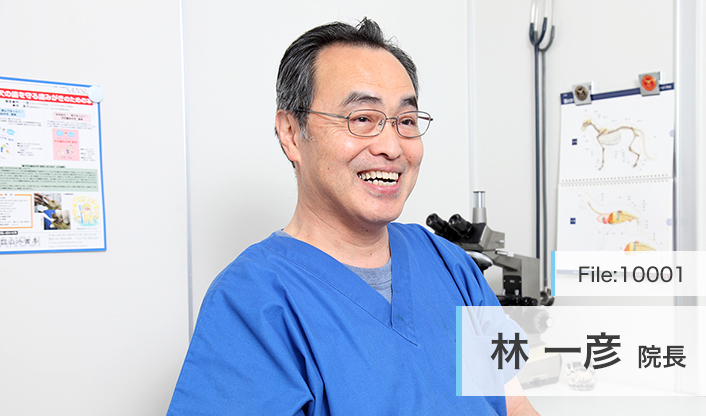
数少なく珍しい、動物の歯科を専門とする「動物歯科クリニック 花小金井動物病院」。林一彦院長はイギリス留学も果たし研鑽を積んできた、動物歯科のエキスパートである。同院では動物への負担に配慮しており、できるだけ抜歯や麻酔を用いた歯科治療を行わない診療方針を掲げているという。予防歯科も重視しており、自宅での口腔内ケアに関する啓発にも尽力している。「頼りにして来てくださっている皆さんのお役に立てるように活動していきたいと思っています」と明るく元気な笑顔で話す林院長に、開院の経緯や注力している取り組み、心がけていることなどをたっぷりと語ってもらった。(取材日2024年12月20日)
数少ない、歯科を専門とする動物病院
林院長は動物歯科を専門とされる獣医師だそうですね。

獣医学部を卒業後、指導教授に当時大学に新設された歯学部への就職を勧められました。もともとは2~3年したら辞めようと思っていましたが、在学中に高い競争率だったイギリスにある大学へ留学し歯の研究をする機会を得たこともあり、辞めづらくなってしまいました(笑)。ただそこでの経験は、その後の僕に大きな影響を与えてくれました。イギリスに渡ってすぐ、軍用犬の歯科治療を見させてもらえたのですが、医学部と歯学部、獣医学部が密に連携しながら治療にあたっていました。日本では考えられないことだったので、強いカルチャーショックを受けましたね。将来は留学で得た動物歯科の知識・技術を生かしながら、獣医師として社会に貢献したいと考えるようにもなりました。帰国後は歯科博士号を取得し、後に大学に動物歯科センターを新設し、臨床を行いながら、今につながる研究に従事。2013年に動物の歯科を専門とする動物病院を開院しました。
なぜ、歯科専門の動物病院を開院しようと思われたのでしょうか?
一般的に町の動物病院では、1人の獣医師が全診療科を診るのが当たり前でしょう。ですが私は、人間の医師のように獣医師も専門性を高めて、診療科を分けるべきだと考えています。また歯石除去のために動物病院へ行くと、基本的に全身麻酔を用いた治療法を提案される傾向があります。その場合「全身麻酔での治療は避けたい」と考える飼い主さんは、無麻酔に慣れていないが対応はしてくれる場所を頼らざるを得ません。しかし無麻酔に慣れていない場所で無理に治療を進めると、やはりトラブルにつながってしまうことに……。こうした状況に我慢ならず、歯科専門の動物病院を開院しました。当時はまだ世界的に見ても珍しいことであり、開院は勇気のいることでしたが、これまでの研鑽で培ってきた知識と技術に自信がありましたので思い立つことができましたね。
こちらではどのような診療を提供しているのでしょうか?

犬と猫を対象に、口腔内に関する多様な相談や悩みに対応しています。「口腔内の汚れが取れなくなった」「口臭が強くなった」「歯の色が変わってきた」「歯磨きをさせてくれない」といった相談が多いですね。疾患としてはほとんどが歯周病と、固いガムやおもちゃなどによる歯の破折や剥離です。乳歯から永久歯に生え替わる頃から、高齢のために一般的な動物病院での歯科治療が困難な子まで、幅広い年齢の動物を診ています。市内からの受診が中心ですが、近隣の市や東京都23区内、他県などの遠方から足を運んでいただく場合もあるんですよ。
動物を第一に考えた、無麻酔歯科治療と予防歯科に尽力
こちらの診療方針は何ですか?

動物への負担に配慮し、抜歯や麻酔を用いた歯科治療は最終手段として、まずは予防に尽力するという方針です。永久歯は一度抜いたら二度と生えてきません。歯周病予防のために抜歯するとなると、抜歯しただけでは歯周病の完治はめざせませんし、再発するたびに抜歯を続けることとなってしまいますからね。また抜歯をすると顎の骨が軟弱になり、骨折しやすくなってしまいます。こうした理由から、すぐに最終手段を選ぶのではなく、先に他の方法で口腔内の環境整備を図り、痛みや不快感の緩和につなげることを優先しているのです。もちろん抜歯は必要な状況もありますから、その際は適切な判断に努めています。
歯科治療は基本無麻酔とされている理由を、さらに詳しくお聞かせください。
動物の歯科治療では全身麻酔をかけるのが一般的ですが、人間の歯科治療では基本的に全身麻酔をしないことと、動物の全身麻酔は体への負担が大きいこと。これらを受けて、獣医療も人間の医療に近づけたい、歯科治療の負担を減らしたいと考えるようになり、当院ではできるだけ麻酔を用いないようにしているのです。治療を安全に進めるために、動物1頭に対して必ず獣医師とスタッフが二人一組となり対応。基本は消毒や歯ブラシで菌を取り除いた後、ハンドスケーラーで歯石を除去し、最後に薬を塗布するという流れです。治療の際は動物への負担を考慮し、できるかぎり短時間で終わるように心がけています。また動物が環境に慣れてから治療を進めるようにしていますが、それでも嫌がる子には無理強いしないのでご安心ください。飼い主さんに複数の選択肢を提案することも獣医師の仕事だと考えています。ご希望に沿った診療を提供できるように今後も尽力します。
予防歯科の啓発にも力を入れているそうですね。

治療には積極的ですがケアには注力しないため、再発を繰り返し、最終的に高齢になった時に麻酔を用いた歯科治療ができずに困り、当院へ駆け込むというケースがよくあります。また「歯石がついたら歯周病になってしまう」「汚れや吸収病巣は虫歯」と勘違いしている飼い主さんも多いですね。予防の重要性をお伝えして飼い主さんのデンタルIQの向上につなげることも、私たちの役割の一つ。ですから当院では診療の際に、動物の口腔内の環境は人間と異なることや、ケアのやり方や重要性をご説明しているのです。歯磨き教室や個人レッスンも行っています。ケアについて話す際は、あくまでもしつけの一環であり、頑張りすぎず時間をかけなくて大丈夫であること。動物とのコミュニケーションと捉えて、楽しみながら行うことが大事だとお伝えしています。ケアに慣れてもらえれば、当院での歯科治療をはじめ、他の診療もスムーズに行えるようになるでしょう。
動物と飼い主にとって「良い」動物病院をめざして
動物や飼い主さんと接する際に心がけていることはありますか?

動物と接する際は、プレッシャーや警戒心を与えないことを意識しています。まずは動物病院という環境や私たちに慣れてもらうことを第一に、かわいがったり褒めたりします。そうした「対話」を続け、信頼関係を築いてから治療を進めていますね。一方飼い主さんに対応する際は、できるだけ気持ちに寄り添うことを重視しています。厳しいことを言う場合もあるのですが、それは飼い主さんにとって大切な家族である動物を思い、真摯に向き合っているからこそだと知っていただけましたら幸いです。
今後の展望・目標をお聞かせください。
導入したいものや新しく始めたいことがいろいろとありますが、まずは現状を維持しつつ、一組でも多くの動物と飼い主さんに貢献したいですね。そして動物にとっては楽しく安心できる、飼い主さんにとっては相談しやすい動物病院でいられたらうれしいです。また、市販の動物用の歯ブラシやケア用品ではなかなか理想のものがないと感じています。以前近隣の施設と協力してよく噛める犬用おやつを開発したことがあるので、将来また新たに何かを開発したいと思っています。こうした活動をきっかけに、地域社会の盛り上がりにもつながったら何よりです。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

歯周病は一度発症してしまうと治らない病気です。しかしかからずに過ごすことも難しい病気でもあるので、かかってしまった場合はいかに進行を遅らせられるかが大切になってきます。「私がケアをちゃんとしなかったから……」とただ後悔するのではなく、今からその子に何をしてあげられるかを一緒に考えていきましょう。そして愛犬、愛猫のQOLを伸ばしてあげましょう。

